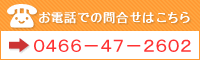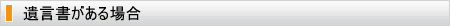
相続が発生した場合に、まず始めに行わなければならないのは、遺言書があるかないかを確認することです。遺言書がある場合とない場合とでは、相続手続きがかなり異なってきます。
また、相続人全員で遺産分割協議を終えたあとに遺言書が見つかると、遺産分割協議をもう一度やり直さなければならない場合もあります。遺品を整理しながら、遺言書が保管されていそうな場所を徹底的に調べましょう。
また、亡くなられた方が、公正証書遺言を作成していた場合、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用すると便利です。相続人等の利害関係人であれば、最寄りの公証役場で遺言書があるかないかを確認してもらうことができます。その際、遺言者及び相続人等請求者の戸籍謄本、請求者の身分証明書(運転免許証)が必要になります。
遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません。遺言書がある場合には、家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続きを受けなくてはなりません。
この「検認」の手続きは、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するためのものです。検認を怠ったり、勝手に遺言書を開封したりしても遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料の処せられます。また、検認をしないと相続登記や預金通帳等の相続手続きが行えません。
なお、見つかった遺言書が公正証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。
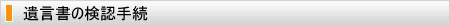
遺言書検認の手続きは、遺言書を保管していた人や遺言書を見つけた相続人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てて行います。申し立てに必要な書類は以下の通りです。
申立てに必要な書類
①申立書 1通
②申立人、相続人全員の戸籍謄本 各1通
③遺言者の戸籍謄本等(出生時から死亡までのすべての記載のあるもの) 各1通
④遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
なお、当事務所では検認手続の代行も行っております。ご相談ください。
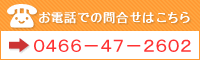
|