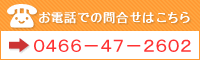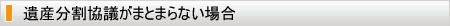
 先日父が死亡し、相続人である私と兄と妹の3人で何度も遺産分割協議をしたのですが、誰がどの財産を取得するかでもめて、なかなか協議がまとまりません。どうしたらよいでしょうか?父は遺言書を書いていませんでした。 先日父が死亡し、相続人である私と兄と妹の3人で何度も遺産分割協議をしたのですが、誰がどの財産を取得するかでもめて、なかなか協議がまとまりません。どうしたらよいでしょうか?父は遺言書を書いていませんでした。
 まずは、弁護士等の法律に詳しい中立で信頼できる第三者に遺産分割協議に立ち会ってもらいましょう。それでも遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。 まずは、弁護士等の法律に詳しい中立で信頼できる第三者に遺産分割協議に立ち会ってもらいましょう。それでも遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停が成立しなかった場合には、自動的に遺産分割審判手続に移り、家事審判官(裁判官)によって遺産分割の審判(判決のようなもの)がなされます。
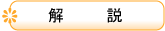
遺言書がない場合、法定相続分以外の割合で遺産を分割するには、相続人全員が遺産分割協議の内容に合意しなければなりません。1人でも協議に反対の相続人がいるなら、遺産分割協議は成立しません。
遺産分割協議では互いの利害が衝突しあい、たとえ親族であってもなかなか話し合いがまとまらないケースがあります。特に当事者である相続人だけの話し合いでは、収集がつかなくなることもあるでしょう。
弁護士等の相続に詳しい信頼できる第三者に、遺産分割協議に立ち会ってもらうなら、
中立の立場から法的な意見を聴くことができ、相続人全員が納得できる公平な遺産分割ができるかもしれません。
また、不動産などの遺産があるならば、不動産鑑定士等の専門家に遺産を評価してもらうなら、遺産をより公平に分割できるでしょう。
それでも協議がまとまらない場合には、次の家庭裁判所の遺産分割調停手続きを利用します。
 遺産分割調停手続 遺産分割調停手続
遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割協議に賛成しない相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産分割調停の申し立てをします。
【必要書類】
①申立書
②亡くなられた方の戸籍謄本等(出生から死亡した記載のあるものまですべて)
③相続人全員の戸籍謄本・住民票
④遺産のリスト
⑤不動産の登記簿謄本(遺産に不動産がある場合)
⑥固定資産評価証明書(遺産に不動産がある場合)
申し立てが無事受理されると、裁判所から相続人全員に呼出状が送られてきます。
調停手続きでは、2人の調停委員(弁護士や民生委員など)と1人の裁判官が立ち会い、対立している相続人を1人ずつ交互に調停室に呼び、それぞれの意見や希望を聞きます。
調停委員は、それぞれから聞き取った希望や解決策を相手の相続人に伝え、それを何度も繰り返して、妥協点や解決策を探っていきます。
相続人全員が納得し調停が成立すると、調停調書が作られます。調停調書は判決と同じ強い効力があるので、たとえ後で心変わりをした相続人が調停調書に反対しても、調停調書どおりの相続登記や強制執行を行うことができます。
一方、遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合には、次の遺産分割審判手続きに移ります。
 遺産分割審判手続 遺産分割審判手続
審判手続きでは、家事審判官(裁判官)がそれぞれの相続人の年齢、職業、生活状況、心身の状態等や遺産の種類等を考え、また、それぞれの相続人の意見を聞いたうえで、遺産分割の内容を決定します。
審判の決定も判決と同じ強い効力があるので、調停調書どおりの相続登記や強制執行を行うことができます。
尚、相続税がかかるケースでは、遺産分割協議が成立しないまま何年も経過してしまうと、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例等、相続税の軽減を受けられなくなることがありますので注意が必要です。
|